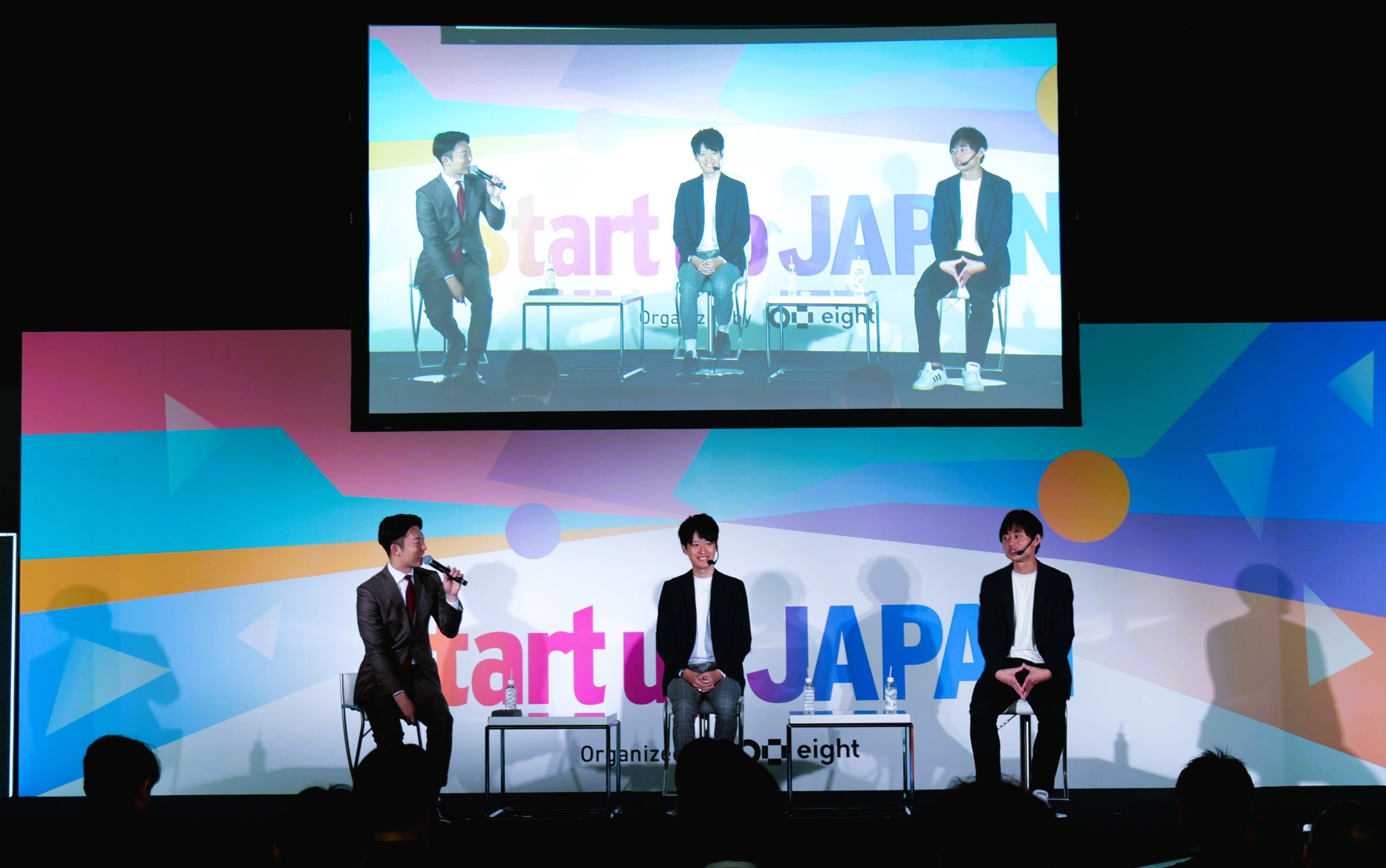
2024年11月20〜21日、国際展示場で日本最大級のスタートアップ専門展示会が開催された。本イベントではスタートアップに関心のある企業とスタートアップとが交流できる場を提供し、スタートアップ業界の成長を後押しすることを目指している。今回、11月20日に「CVCは、事業会社にとっての切り札?新規事業、イノベーション創出を目指したCVC活動における課題と未来」と題し、現在のCVC活動とこれからのイノベーションに関してNTTドコモ・ベンチャーズ、TOPPANホールディングス、ソーシングブラザーズ株式会社から代表して三名が語り合った。
写真左から 渡邊祥太郎 氏、今井康貴 氏、高橋琢朗 氏。
NTTドコモ・ベンチャーズ Investment & Business Development Manager
今井 康貴 Yasutaka Imai
NTTドコモに新卒入社後、PRプランナーとしてコーポレートコミュニケーションの分野に長らく従事。経営戦略・出資協業・新規事業・先進技術などの対外発信戦略の立案と実行を担う。2016年からモバイル関連の国際展示会MWC Barcelonaのプロジェクトを手掛け、5G/6GのユースケースやOpen RAN事業などの海外発信を主導。2023年7月にNTTドコモ・ベンチャーズに参画。現在スタートアップとの協創・投資およびPRを担当。
TOPPANホールディングス株式会社
高橋 琢朗 Takuro Takahashi
大学を卒業後、2018年に凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)に入社。CVC部門(当時経営企画本部 戦略投資推進室)に配属となり、10社を超えるベンチャー企業との資本業務提携に従事。資本業務提携先のスタートアップとの事業開発プロジェクトにてサービス開発のオペレーション回りも推進。メトロエンジン、ユニファ、TCM、グラファー、トレタ、Liberaware、Chai、CO-NECTなどを担当。
ソーシング・ブラザーズ株式会社
代表取締役 Co-Founder
渡邊 祥太郎 Shotaro Watanabe
大和証券株式会社に入社し、法人・富裕層向けのウェルスマネジメント業務に従事。その後、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社に入社し、M&Aアドバイザリー業務に従事。
2019年にソーシング・ブラザーズを共同創業し、イノベーションプラットフォーム事業を展開。ヒト・モノ・カネ・情報を展開できるプラットフォーマーとして、CVC運営支援、スタートアップM&A支援、スタートアップ採用支援の3事業を展開。
なぜCVCをはじめたのか
今井:私たちがCVCを立ち上げた理由ですが、やはりこれから日本で新しい価値を生み出していく上で、事業会社にとってもスタートアップの皆さんの力が不可欠だと考えているからです。これはNTTグループ全体の考え方にも通じています。
NTTグループには営業チャネルや人的リソースが豊富にあり、何かを世の中に広めたり、社会実装していくといった部分は得意としています。ただ一方で、ゼロから新しい事業を作り出すという点では、正直なところ課題が多いと思っています。
そのため、スタートアップの皆さんが持つ「事業構想力」と、私たちNTTグループの「社会実装力」を掛け合わせることで、世の中に新しい価値を生み出し、それを広げていけるのではないかと考えています。そして、CVCはまさにそのプロセスを推進する役割を担うための存在だと思っています。
渡邊:ありがとうございます。続いてTOPPANさんにもお伺いできればと思います。
高橋:私たちが運営しているCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)は、バランスシートから直接投資を行う形態をとっています。ただし、本体の経営会議や取締役会で決裁を取るとなると、どうしてもプロセスが煩雑化し、スピード感が失われる課題がありました。そのため、執行役員に予算と決裁権限を持たせ、譲渡や投資に関する意思決定を答申会で完結できる仕組みを整えています。これにより、より迅速な対応が可能となっています。
CVCの運営自体は2016年7月にスタートし、現在8年目に入っています。当社はもともとBtoBの事業を主軸に、ソリューションを構築しお客様に提案する活動を行ってきました。ただ、ソリューションが早期にコモディティ化してしまうという課題や、自社のみで新たなソリューションを作り続けることの限界も感じていました。
そこで、当時注目されていた「オープンイノベーション」の考え方を取り入れ、CVC活動を開始しました。スタートアップの皆さんの力を借りながら、一緒に新しい事業やソリューションを創出することを目指したのが背景です。CVCを通じて、スタートアップとの連携により、既存の枠組みを超えた革新的な取り組みを進めています。
CVC投資スキームについて
高橋:私たちの活動の軸としては、「戦略リターン」を重視しています。もちろん、出資活動である以上、財務リターンも重要視しています。具体的には、株式のバリュエーションや事業計画の実現可能性、成長戦略などを慎重に見極めながら進めています。ただ、社内から最も期待されているのは、やはり戦略リターンの部分です。
戦略リターンは非常に奥が深く、明確に一つの形で定義するのは難しいのですが、最終的なゴールとしては、スタートアップの皆さんとともに新しい事業を共創することだと考えています。ただし、このプロセスにはさまざまな時間軸や段階があります。
まず初期の段階では、スタートアップのサービスを私たちのチャネルで販売する、あるいは私たちのサービスとスタートアップのプロダクトを組み合わせて販売するといった形で協力を進めます。その後、一緒に新しいサービスを開発したり、事業を創り上げていくステップに移行していきます。
さらに中長期的な視点では、M&Aを通じてスタートアップをグループに迎え入れたり、ジョイントベンチャーを立ち上げて共同で事業を展開していくといった取り組みも視野に入れています。こうした多様な形での共創を通じて、戦略リターンの実現を目指しています。
渡邊:マジョリティでM&Aしていくことも確かご経験としてはありますよね。
高橋:今まで70社出資して3社の会社さんに凸版グループにジョインしていただきました。
渡邊:やはり、出資からM&Aに至る流れというのは、CVCの活動において非常にわかりやすいアウトプットの一つだと思います。最初はマイノリティ出資としてスタートした複数のスタートアップの中から、最終的に成長し、私たちの事業会社としてシナジーを発揮できる企業を見極める。そして、その企業を保有比率51%以上の形で迎え入れる――こういったプロセスは、CVCの理想的な姿だと考えています。
このように、単なる出資にとどまらず、スタートアップとともに事業を成長させ、その関係性を深めていくことが、私たちが目指す共創の形です。その結果としてM&Aが実現するというのは、非常に意義深い成功例だと思っています。
今井:基本的な考え方は、TOPPANホールディングスさんと似ている部分が多いと思います。我々も戦略リターンを重視するというスタンスを取っています。もちろんファンドとして財務リターンを意識することは前提ではありますが、どこにリソースを注ぐべきかという点では、いかに戦略リターンを出せるかが重要です。
スタートアップの皆さんがCVCに何を期待して相談に来てくださるかを考えると、やはり事業シナジーや戦略リターンの部分が大きいのではないかと思っています。そのため、我々も単にIPOをゴールとするだけでなく、連携によって生み出せるシナジーを最大化する協業支援の活動を重視していますし、その延長として、例えばM&Aによって事業部の一員になっていただくようなアプローチの仕方も、まさに強化をし始めているところです。
ただ、正直なところ「戦略リターン」という言葉自体が非常に難しい概念だとも感じています。特にCVCや事業会社の目線で考えると、どの案件がどれだけ戦略リターンを生み出すかを測ることは大きな課題と言えるでしょう。我々NTTドコモ・ベンチャーズは16年間活動してきましたが、この「戦略リターン」の定義や伝え方については、常に試行錯誤しています。経営層とのコミュニケーションにおいても、この戦略リターンの重要性をどう伝え、どう共有していくかは、引き続き取り組むべき課題だと考えています。
事例の紹介
今井:NTTドコモ・ベンチャーズは、これまでの16年の歴史の中で累計200社以上への出資を行い、協業の実績も100件以上に上ります。さまざまな形でスタートアップの皆さんとNTTグループの力を掛け合わせて成果を生み出していますが、本日はその一例として、ファイルフォースとNTT東日本が連携した事例をご紹介します。
ファイルフォースというスタートアップは、ドロップボックスのようなクラウドストレージを提供している日本の企業です。このスタートアップとNTT東日本が協力し、「ワークストレージ」という新しいサービスを立ち上げました。
ファイルフォースは、特に日本の中小企業向けに、直感的で分かりやすいUI/UXを追求したサービスを展開しており、IT活用に苦手意識を抱えている企業にも使いやすいと評判です。一方、NTT東日本は、地域の中堅・中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する営業活動を行っていますが、コロナ禍でリモートワークが進む中で、従来のサービスでは十分にお客様の期待に応えられないという課題を抱えていました。
そこで、私たちドコモ・ベンチャーズがこの2社を引き合わせ、協業の検討がスタートしました。ファイルフォースが持つ分かりやすいUI/UXや技術力と、NTT東日本が誇るセキュリティやネットワーク技術を融合させ、2021年に「ワークストレージ」というサービスを共同開発しました。
このサービスは、ターゲットを明確に設定したことや、アジャイル開発でスピーディな提供を実現したことで大きな成功を収め、サービス開始から1年半で累計契約数が2万件を超える成果を上げました。現在では、NTT東日本の主力サービスの1つといえるほどの規模に成長しています。
この事例は、スタートアップの事業構想力とNTTグループの社会実装力を組み合わせることで、社会に新たな価値を提供する好例だと考えています。
渡邊:まさに冒頭でお話ししたように、スタートアップの事業構想力とNTTグループの実装力を掛け合わせることで、社会に新たな価値を提供できた事例の1つだと考えています。まさにオープンイノベーションの好例と言えるでしょう。大企業が持つ顧客基盤を開放し、それにスタートアップが持つ独自の技術を組み合わせて、新たな価値を創出する。その実践が今回の共同サービスによって実現できたと思います。
高橋:我々は、グラファーさんという自治体向けのガバメントテック(GovTech)サービスを展開している企業と、2020年7月から共創活動を行っています。この共創事例では、現在「ハイブリッドBPO」と呼ばれるサービスを展開しています。具体的には、オンラインとオフラインのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)処理を自治体や金融機関向けに提供しており、特にコロナ禍の給付金申請処理などで重要な役割を果たしています。
このサービスの主な役割は、申請書類の審査や不備のチェックなど、裏方で行われる業務を効率化することです。グラファーさんが提供する「スマート申請」や「窓口予約」のような自治体向けのデジタル化サービスと連携し、自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。特に、フロント部分(住民からの申請や自治体内での効率化)のデジタル化が進んでいる中で、裏側の処理やアナログ業務の効率化が求められており、このニーズに応える形で連携しています。
この共創は、自治体のデジタル化を進めるために、グラファーさんのフロント部分のサービスと、我々が得意とする裏側の業務処理を組み合わせ、自治体向けに共同で提案を行うという形で実現しました。実際には、大阪市などの自治体に対して共同提案を行い、いくつかの事例を成功させています。双方が「やりたいけれどできない、やりたくない」と感じていた部分をうまく掛け合わせて、実現した事例だと言えると思います。
CVCの現状を渡邊が振り返る
渡邊:今回提携例を教えていただきましたが、実際は事業提携や協業の過程で直面する課題は非常に多いです。特に、スタートアップとの連携においては、いくつかの困難な点があると思います。
1つは、スタートアップとのコミュニケーションが難しいという点です。大企業とスタートアップでは、企業文化や意思決定のプロセスが大きく異なるため、互いの期待や価値観を理解し合うことが最初の壁となることが多いです。例えば、スタートアップ側はスピードや柔軟性を重視し、大企業側は慎重で規模を意識した行動を取ることが多いため、協業の進め方やペースを合わせることが難しくなります。
さらに、提携を進めても、実際に新しい事業や利益が生まれないケースもあります。これは、スタートアップのサービスを利用するだけでは、真の価値創造に繋がらない場合があるからです。新しい事業を生み出すためには、単にサービスを使うだけでなく、双方がどのようにしてリソースや技術を組み合わせ、付加価値を加えていけるかが重要になります。この点がうまく機能しないと、せっかくの協業も期待した成果に繋がらないことになります。
こうした課題を乗り越えるために、いかに柔軟にコミュニケーションを取るか、互いの強みをどう活かすか、そして最終的にどのように事業としてスケールさせるかが重要です。
日本におけるCVCの増加や事業会社の取り組みは、スタートアップエコシステム全体を大きく変える力を持っていると思います。10年前はCVCの数がわずか20社程度だったところから、今では設立されているCVCだけで200社以上、さらに投資を行う事業会社全体では年間1000社にも及ぶという急成長を遂げています。この変化が示すのは、事業会社がスタートアップとの連携を通じてイノベーションを生み出す重要性を強く認識し始めたということです。
実際、新規事業に取り組む事業会社やその担当者、役員の方々と話をしていると、構想やアイディア自体はあるものの、それを実行に移す上でのリソース不足という課題をよく耳にします。お金があっても、それだけでは十分ではなく、プロジェクトを具体的に進めるための人的リソースが圧倒的に足りていないという現状です。
特に、イノベーションを推進するための専門人材を採用することが難しいと感じている企業が多いです。プロフェッショナルな人材の獲得が中途採用では難しかったり、社内でそういったイノベーション人材を育成する余裕がないという声も多いです。その結果、スタートアップとの連携が事業創出のための重要な選択肢となり、CVCがその橋渡し役としてますます注目されています。
この課題にどう対応し、スタートアップの力を活用していくかは、今後の日本企業の競争力やスタートアップエコシステムの成熟に直結する重要なテーマですね。
さいごに
渡邊:実際に先ほどご紹介した2社の取り組みを見ても、自分たちが提供できる強みを活かしつつ、足りない部分を新しいスタートアップの技術や開発力、そしてそのスピード感で補うことができる点が、非常に大きなポイントだと感じています。こういったスタートアップとの連携によって、大企業の新規事業開発のスピード感が大きく向上するのではないでしょうか。それこそが、今の時代における大企業の新規事業の作り方の1つの理想形なのかなと、私たちも支援を通じて日々実感しています。
CVCという言葉だけを聞くと、敷居が高そうとか、投資によって利益を上げるための仕組みなのではないか、といったイメージを持たれる方も少なくないかもしれません。しかし、実際にはスタートアップの技術やアイディアを活用し、大企業の新規事業開発を加速させるための重要なツールであり、経済全体の活性化にもつながる仕組みだと思っています。
これからは、「チーム力の民主化」を進めることで、日本全体の経済をもう一度活性化させるきっかけになると確信しています。今日のような取り組みが広がり、CVCを活用した事例が増えることで、日本の企業が新しい価値を生み出し、より強いエコシステムが形成されていくのではないでしょうか。